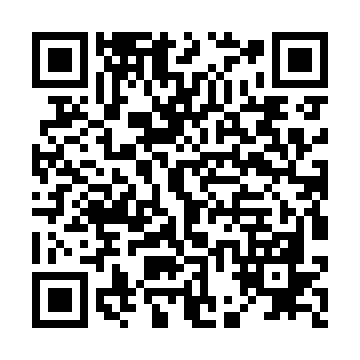学生・社会人必見!実際に一人暮らしをする前にかかるお金、年間更新費用や火災保険ってどんなものなのかご紹介します!
ひと昔前に比べて、テクノロジーの発展により頻繁に人が移動する時代になり、マンションやアパートなどの賃貸物件を数年単位で借りる人が多くなりました・・
それに伴い、不動産の賃貸契約を結ぶ機会も増えてきていますよね。
その際に多くの人が感じることは、新しい住居を借りる際に、
「意外と多額の現金が必要なんだね・・・ガックシ・・・」
そんながっくしにならないためにも、予備知識をつけるため、
今回は家賃以外にかかる費用について詳しくご説明します。
ソモソモ、不動産賃貸契約とは?
引っ越しにかかる諸々の費用をご説明する前に、
「嗚呼、そもそも不動産賃貸契約とは何ぞや」ってことです。
わかっているようで、いざ説明するとなるとちょっと難しい、この問題から見ていきましょう。
民法では、私たちの日常生活に関する決まりごとが書かれています。
その中でも特に重要なのが「契約」です。
日常生活には、実に多くの契約がありますが、それらの中で「賃貸契約」というのは、
ある人が持っているものを借りる代わりに、賃料を支払う契約のことです。
そして借りるものが、マンションやアパート、土地などの不動産の場合を「不動産賃貸契約」と言います。
この契約では、貸す人は借りる人に目的物(マンションやアパートなど)を使用収益させる義務を負います。
その代わり、貸す人は目的物の使用収益に必要な修繕義務を負うことになるのです。
一方、借りる人は目的物を借りる対価として、賃料(家賃)を支払わなければなりません。
また、賃料以外にも共益費や更新料などの費用を負担することになります(この点は後述します)。
以上が、不動産賃貸契約の概要です。
不動産賃貸契約にかかる2つの費用とは?
不動産賃貸契約にかかる費用には、大きく分けて2つあります。
「契約時に負担する費用」と「契約後に負担する費用」です。
「契約時に負担する費用」としては、主に敷金、礼金、仲介手数料の3つです。
「契約後に負担する費用」としては、主に家賃、共益費、年間更新費用、火災保険の4つです。
◆契約時に負担する費用について
【敷金】
まずはこれは借主が賃貸借契約を解除して、借りていた物件を引き払うときに、物件の原状回復のための「修繕費」に充てるものです。
ただ、経年劣化と言って、年数が経って自然に損傷した部分は家主の責任において修繕を行います。
しかし、借主が故意または重大な過失によって、物件が損傷などをした場合に、この敷金が充てられることになるのです。通常、敷金は家賃の3~4ヶ月分です。
従って、借主に故意または過失が全くなければ、理論上敷金がそのまま戻ってくることになります。
しかし、多くの場合そのようなことはありません。
借主が何年も住んでいて、経年劣化以外に全く汚さずに生活することはあり得ないからです。
ですから、家主の言いなりになって、借主の責任として敷金から原状回復費用をねん出されているケースも残念ながらあります。
借主が賃貸借契約を解除して物件を引き渡す際に、最も多いトラブルがこの敷金返還の問題です。
そこで、国土交通省では、どのような場合に敷金を補修代に使ってよいかの「ガイドライン」を作成しています。
敷金返還を求める場合は、借主はこのガイドラインを十分に確認しておく必要があります。
【礼金】
賃貸借契約を結んだ家主に「お礼」として支払うものです。通常、家賃の1ヶ月分程度です。
【仲介手数料】
これは借主と家主の間を仲介した不動産管理会社などの手数料となります。こちらも、通常家賃の1ヶ月分程度です。
その他に、だいたい契約時には最初の家賃1ヶ月分の支払いを行うことになりますから、
合計で家賃の6~7ヶ月分の金額が、契約時に必要となります。
敷金礼金以外にかかる費用と節約方法について詳しくはこちらに記載しています。
◆契約後にかかる費用について
前述した通り、「契約後に負担する費用」としては、主に家賃、共益費、年間更新費用、火災保険の4つです。
家賃はご存知だと思うのでここでは説明しないのでそれ以外の3つをご紹介します。
【共益費】
ほとんどのマンションやアパートでは、「家賃+共益費」という表示で毎月支払う金額を借主に示しています。「共益費」ではなく、「管理費」という表示もありますが、本質的には同じです。
また、家賃のみを支払う物件も存在しますが、このような場合、家賃の中に共益費を含んだ形で、家主が借主に請求する仕組みになっています。
つまり、物件を借りている以上は、共益費を必ず負担することになっているのです。
借主が家賃と一緒に支払っている「共益費」ですが、多くの人が何のために使われているのか、よく理解されていないのが事実です。
一言で言うと、「共益費」という言葉どおり、建物の共用部分の維持費に使用されます。
共用部分とは、マンションやアパートの玄関、廊下、エレベーターなどで、その修理費や電気料金に使われています。
また、浄化槽の保守点検に要する費用も共益費に該当します。
このように、実際に借主が借りている部屋以外の公共物のための費用として、使われています。
共益費の金額の決め方には、一定のルールがあります。
まず物件の共用部分の維持管理にかかる費用を算定し、その上で借主の住戸の面積に応じて分配する方法で、金額を決めていきます。
従って、共用部分の規模などによって、維持管理の費用は物件ごとに異なるため、同じマンションに住んでいても、借主の住戸ごとに、共益費が違ってくる可能性があります。
【年間更新費用】
新たにマンションやアパートなどに住む際に、賃貸借契約というものを結びます。
その際に、契約期間を定める場合がほとんどで、
物件、あるいは不動産管理会社によって、その年数は様々ですが、1年間、あるいは2年間を契約期間としていることが多いようです。
契約期間が決まっていますから、その期間が終われば契約の終了となりますが、不動産賃貸借契約では、契約の更新ということが、契約時に交わす「賃貸借契約書」に記載されています。
この契約の更新方法についても、物件、不動産管理会社によって様々ですが、
多くの場合「契約を更新しない場合は、遅くとも1ヶ月前までに借主から大家さんに通知すること」と決められています。
例えば、借主が2018年4月1日にある物件を借りるための「賃貸借契約」を結び、契約期間が2年間だとします。2020年3月31日で契約満了になりますから、2020年2月28日までに、借主から大家さんに契約更新をしないと伝えない限り、自動的に契約更新となるのです。
ただ、契約更新料がある契約の場合、契約満了の2,3ヶ月前に、契約更新の案内と更新料の振込用紙などが届きます。
契約を更新したいときには、更新料の振込みを行います。一方、更新する意思がないときには、期限までに大家さんに連絡をすることになります。
上記の説明で、「契約更新料がある契約の場合」と書きましたが、更新料を徴収しない契約もあります。
この違いは、契約を結ぶ際に更新料の規定があるかないかの違いです。
借主の中には、「ただ契約を更新するだけなのに、なぜ更新料を取られるだろう」と疑問を持つ人がいるかもしれません。
しかし、2011年7月15日の最高裁判決で「更新料は賃料とともに賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であり、その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからすると、更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。」として、契約更新料が妥当だとされました。
つまり、、
更新料は大家さんの収益の一部となっており、しかも家賃の金額を超えるなどの特別高額な金額でない限りは適法である、という判断です。
しかも、契約を結ぶ際に「賃貸借契約書」に明記されているわけですから、借主も納得の上で賃貸契約を結んでいるはずだとの見解なのです。
【火災保険】
ほとんどの不動産賃貸契約では、火災保険の加入が義務付けられています。
通常、契約更新時に、1万円前後の保険料を支払うことになりますが、
この火災保険は大きく分けて「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3つの分野で構成されています。
契約をされる前にしっかり知っておくと良いので、詳しく説明しておきます。
まず、「家財保険」です。例えば、故意または過失によって他人に損害を与えた場合、基本的には、加害者が損害を賠償しなければなりません。これは、民法第709条に規定された「不法行為による損害賠償」に基づくものです。
ただ火災に関しては、「失火ノ責任ニ関スル法律」で、「重大な過失」があるときだけ、加害者の責任が問われます。つまり、通常の不注意程度では、たとえ火事を起こして隣近所に損額を与えても、責任を負う必要がないということです。
そのような事態に備え、他人の火災によって損害を受けた場合に、家財保険に前もって加入しておくのです。
2つ目は、「借家人賠償責任保険」です。
敷金の項目で説明しましたが、物件の借主は賃貸契約が終了したときに、現状を回復した状態で、大家さんに引き渡さなければなりません。
もちろん、年数が経ったことによる損傷など(経年劣化)や通常の使用による損傷などについては、借り主に責任はありません。
しかし、貸主の故意または過失による損傷などは、借主の負担によって、原状回復する必要があります。
そのために、契約時に「敷金」を前もって支払っているわけですが、もし借主が火災を起こして部屋を焼いてしまった場合、敷金の範囲で原状回復ができる可能性はかなり低くなります。
そこで、「借家人賠償責任保険」に加入することによって、借主が失火した場合に備えるのです。
3つ目は、「個人賠償責任保険」です。これは、集合住宅で起きるトラブルに備えた保険です。
例えば、お風呂のお湯を出しっ放しにして、下の階の部屋の住人に損害を与えたとします。
このような場合、加害者が被害者の損害を賠償することになりますが、そのようなときにこの「個人賠償責任保険」が利用できるのです。
以上の3点から構成される火災保険ですから、借主の加入が基本的に義務付けられているのです。おわり!
賃貸情報をもっと知りたいという方はさくっとホームをご覧ください
まとめ
名前が難しい・・・と内容も難しいだろうと詳しく知らないままにしておくと少し損をするかもしれません。
一人暮らしを始める前は、余分なお金を払わないためにも、なににどんな理由で費用がかかるのかを把握して、確認しておくことが必要ですね!
リバフク編集長
最新記事 by リバフク編集長 (全て見る)
- 【社会人・学生必見】一人暮らし前に知っておきたい引っ越し業者の選び方とは? - 2018年11月8日
- 【一人暮らしの前に知っておきたい】電気・ガス・水道の開始の手続きと解約の方法について説明します - 2018年11月8日
- 【一人暮らし前に知っておきたい】物件を借りる際に必要な「保証人」ってどんな人?親族しかだめなの? - 2018年11月8日